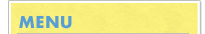ひまわり皮膚科のQ&A
診療についてよくいただく質問を集めました。
質問と回答
1.アトピー性皮膚炎ってどんな病気なの?
2.アトピー性皮膚炎の原因はダニと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
3.アトピー性皮膚炎は乾燥するから病気になると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
4.アトピー性皮膚炎の治療にステロイドのような強い薬を使う理由はなぜですか?
5.喘息がある場合には痒み止めの飲み薬を服用してはいけないといわれましたがどうなのでしょう?
6.アトピー性皮膚炎の治療に抗真菌剤の内服薬を使用するのはなぜですか?
7.他の先生に抗真菌剤は強い薬だから服用しないほうが良いといわれたのですが、どうなのでしょうか?
8.アトピー性皮膚炎では食事にはどのような注意が必要ですか?
9.母親が卵を食べると、母乳を飲んだ乳児に湿疹ができるって本当?
10.蕁麻疹やアトピー性皮膚炎の症状が強い場合には食事はどのようにしたら良いでしょうか?
11.アトピー性皮膚炎では、入浴剤はどのようなものを使用したら良いのでしょうか?
12.アトピー性皮膚炎では石鹸はどのようなものを使用すれば良いのでしょう?
13.アトピー性皮膚炎では保湿剤はどのようなものを使用したら良いのでしょうか?
14.軟膏の塗り方について教えて下さい。
15.子供が粉薬を飲まないのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
16.わきがの治療方法について教えて下さい。
17.ピアスの穴を開けたいのですが、方法や費用について教えてください。
18.下肢静脈瘤の治療法はどのようにするのですか?
19.手術の方法と費用について教えて下さい。
Q:アトピー性皮膚炎ってどんな病気なの?
A:アトピー性皮膚炎にはかなり誤解が多く見られ、いたずらに怖がったり、やたらと民間療法にとびつく人を多く認めます。当院では今までに数百人のアトピー性皮膚炎を診療し治療してきた実績がありますが、アトピー性皮膚炎はけして恐ろしい病気ではありません。ほとんどの人は適切な治療を行えば速やかに症状が改善していきます。
アトピー性皮膚炎は基本的には皮膚や粘膜が敏感であるために湿疹や蕁麻疹ができやすい疾患です。乳幼児では皮膚や粘膜は特に敏感であるためにかなり多くの人がアトピー性皮膚炎を発症しますが、ほとんどの人は成長に伴って症状は改善していきます。
皮膚や粘膜が敏感ですので、さまざまな食物やダニ、洗剤などの刺激により痒みや湿疹を発症します。その結果、検査でもいろいろな陽性反応を示します。しかし、それは食物やダニが原因で起こったものではなく、皮膚や粘膜が敏感であるために生じたものであり、厳密な食事制限やダニ駆除を行うことはほとんど意味がありません。皮膚や粘膜が敏感ですので繰り返し湿疹を再発しますが、それも徐々に成長とともに改善していくのが普通です。けして一生治らない不治の病でもなければ、難治性の疾患というわけでもありません。普通に皮膚や粘膜への刺激を避けて、その状態に応じた治療薬を用いれば簡単に治る病気なのです。一時的に増悪しても、早めに治療すればすぐに症状は良くなりますし、薬もすぐに弱くするか中止することができるのです。やたらと怖がっておかしな治療法を行ったり、湿疹を放置しておくことがもっとも良くないことなのです。普通に適切な治療を行うことがアトピー性皮膚炎ではもっとも大切なことなのです。
Q:アトピー性皮膚炎の原因はダニと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
約三十年前にアトピー性皮膚炎でIgEという免疫グロブリン値が高頻度に高値を示すことが明らかとなり、とくにダニ抗原に反応するIgEが増加することからアトピー性皮膚炎とダニとの関連性が強調されるようになりました。そのため徹底的な掃除を行って、十分なダニ駆除を行うことが推奨されることもありました。しかし、それによって一時的に症状が改善することはあっても、再発しやすくなかなか完治するには至りませんでした。たしかに検査にてダニ抗原で陽性になることが多いのですが、それはアトピー性皮膚炎が刺激を受けやすいことに伴って生じた結果でしかなく、原因とは異なるものと考えられています。
現在はダニは原因というよりも、食事と同様に増悪因子の一つとして考えられています。皮膚が乾燥して敏感なためにダニが付着しやすく、刺激を受けやすいのです。治療にあたってはダニを駆除して少なくすることもある程度有効ですが、それ以上に刺激を受けやすい敏感な皮膚の状態を改善させることの方が重要なのです。
しかし原因とは異なるとしても増悪因子となるものは少ないほうがよいので、布団やカーペットのダニはよく掃除して取り除いておいたほうが良いことは確かです。
最近はダニ抗原に対する過敏反応を改善させる目的で、ダニ抗原を含むまんじゅうのようなものを食べさせる治療(経口免疫寛容)も行われています。
Q:アトピー性皮膚炎は乾燥するから病気になると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
アトピー性皮膚炎の原因としては食物、ダニなどが考えられていましたが、近年は皮膚の脂質の一種であるセラミドの減少が関与することが指摘されています。これは皮膚表面の細胞を接着する糊のようなもので、減少すると皮膚が乾燥してカサついてきます。また種々の刺激に敏感になり、痒みを生じやすくなります。
たしかにセラミドはアトピー性皮膚炎が冬季に乾燥して増悪する要因としては重要なものですが、基本的にはダニや食物と同様に増悪に関係する因子の一つであり、原因とは異なると考えられています。なぜなら一般に小児や老人ではこのセラミドの産生は減少しており、乾燥しやすいからです。しかし、乾燥しても必ずしも湿疹になるわけではなく、またアトピー性皮膚炎ではあまり乾燥しない腋窩や肘・膝などに湿疹が好発する特徴があります。しかし原因とは異なるとは言っても、乾燥はアトピー性皮膚炎の重要な増悪因子であり、とくに乾燥しやすい小児や老人では冬季に湿疹が増悪することが多く認められます。
セラミドは油の一種ですので、石鹸などで洗浄することにより脱落します。しかもいったん脱落すると新しく産生されるまでに2~3週間がかかるために容易には再生しません。乾燥が強い人は石鹸を使いすぎないようにすることが必要です。
セラミドの産生は体質的な因子により左右されるので、乾燥しやすい人は毎冬に乾燥が増悪します。なるべく乾燥しないように、保湿剤などを使用して皮膚を上手に保護するようにして下さい。
Q:アトピー性皮膚炎の治療にステロイドのような強い薬を使う理由はなぜですか?
ステロイドは正式には副腎皮質糖質ステロイドホルモンといい、本来生体で産生されているホルモンの一種です。ステロイドについてはかなり誤解が多く認められますが、このようにもともと人間の体の中で産生されているものですので、けして非常に危険な薬剤というわけではありません。
むろんたいへん有効な薬剤でありますので、誤った使用法をしたり、安易に使用を中断したりした場合には一時的にもともとの症状が増悪することがあります。しかしこのようなリバウンド現象は血圧の薬であれ糖尿病の薬であれ、ある程度の効果のある薬剤を不適切に使用した場合には必ず認められることであり、適切な使用法を行えば生じないことです。
ステロイドの副作用が問題となったのは、十数年以前に発売されていたステロイド外用剤が比較的副作用が強かったことによります。最近のステロイドは以前のものに比較して効力が強い割に副作用が少なくなってきており、以前のような問題はほとんど認められなくなっています。
むしろステロイド以外の薬剤の方がずっと強い副作用を生じることがあり、注意が必要です。さらにアトピー性皮膚炎のような慢性の湿疹の場合には、病気を放置しておくことの方が薬剤による副作用よりももっと重篤な後遺症を生じることも多いのです。ステロイドは強い薬ですが適正な使用法を行えばけして危険な薬ではありません。病気をきちんと治すことの方がずっと重要なのです。
Q:喘息がある場合には痒み止めの飲み薬を服用してはいけないといわれましたがどうなのでしょう?
痒み止めは抗ヒスタミン剤ともいわれ、痒みの原因となるヒスタミンの作用を抑制する薬剤です。第一世代の抗ヒスタミン剤は副作用として眠気や粘膜からの粘液の産生を抑制する作用が強く認められました。そのため喘息でこのような抗ヒスタミン剤を使用すると喀痰の排出が抑制されて喘息の症状を増悪させることがあるため、喘息では痒み止めを服用してはいけないといわれてきたのです。
しかし、その後抗ヒスタミン剤も改良が進み、第二世代の抗ヒスタミン剤はこのような粘液の産生を抑制する作用は以前のものに比較してかなり軽減しています。さらに第三世代として最近になって発売されてきている抗ヒスタミン剤ではほとんど眠気を起こさない薬剤も開発されてきています。そのような理由により、現在では喘息では痒み止めは服用してはいけないという常識はあまり適当ではなくなってきているわけです。
喘息ではアトピー性皮膚炎をしばしば合併するために、その痒みを抑えることがしばしば困難になります。そのような場合でも粘液の産生をあまり抑制しない痒み止めを服用することにより、喘息を増悪させないでアトピー性皮膚炎の痒みを抑制することが可能となります。
いっぽうで花粉症のように鼻汁が大量に排出されるような状況にある場合には、粘膜からの粘液の産生を十分に抑制する必要があるので、あえて第一世代の抗ヒスタミン剤を用いることもあります。このように薬剤は上手に選択を行えば、粘液の産生を抑制するという副作用でさえも治療に有効に行かすことができるのです。
Q:アトピー性皮膚炎の治療に抗真菌剤の内服薬を使用するのはなぜですか?
アトピー性皮膚炎の原因としてはダニ、食事、乾燥などのさまざまな要因が指摘されていますが、いずれも決め手となる因子ではありません。乾燥肌は確かにアトピー性皮膚炎でしばしば認められますが、アトピー性皮膚炎の強く消長を繰り返す痒みを説明することができません。
近年この痒みの原因として注目されているのが胃腸に生息している細菌やカビの影響です。カンジダと呼ばれるカビの一種のほかに胃炎や胃潰瘍の原因とされるピロリ菌なども関与すると考えられています。これらの細菌は胃腸内において増殖し、胃腸粘膜を刺激して食物性蛋白質の吸収を促進するほか、自ら菌体外毒素を産生し痒みなどの種々の炎症性反応を起こすことが知られています。
そのような理由により蕁麻疹や痒みの強いタイプのアトピー性皮膚炎の治療にピロリ菌やカンジダの除菌治療が、とくにアレルギーの専門医によって最近良く行われるようになり、有効な治療効果を上げているのです。
このような胃腸内の病原菌は通常はあまり増殖せずに安定していて、毒素もそれほど産生してはいませんが、風邪などにより体調が変化したときや飲酒や刺激物の摂食により粘膜が刺激を受けた場合には、急に増殖が活発になり種々の皮膚症状を惹起することがあります。
現在はアトピー性皮膚炎において、あまり厳密な食事制限を行うことを指導することはありませんが、胃腸を健康に保つことはアトピー性皮膚炎の治療の上ではやはり重要と考えられているのです。
Q:他の先生に抗真菌剤は強い薬だから服用しないほうが良いといわれたのですが、どうなのでしょうか?
当院でアトピー性皮膚炎などの治療に用いている抗真菌剤は一般名をアンホテリシンBと言って、腎臓への毒性が強い薬剤としてよく知られています。
たしかに注射によってこの薬剤が体内に入った場合には腎臓に強い影響を与え、腎臓病の副作用を生じる可能性があります。しかし、この薬剤を内服した場合には胃腸からはまったく血液中には吸収されないという特性も有しています。そのため胃腸の中に存在するカビの発育を抑制する効果はありますが、この薬を内服することにより腎臓病を発症するということはまったくありません。
この薬剤は近年アトピー性皮膚炎や乾癬・掌蹠膿疱症などのさまざまな皮膚病の治療薬として用いられており、たいへん高い有効性をあげている薬です。いっぽうで小児用のシロップも発売されており、小児が内服しても安全で、とくに支障がない薬でもあります。
この薬にたいして十分な知識のない医師は、この薬が腎毒性を有するということだけの知識により、強い薬だから服用しないほうが良いと指導することがありますが、これはまったくの誤解によるものです。この薬は内服により使用した場合には生体内にはまったく吸収されず、胃腸のみをきれいにしてくれる薬ですので、どうぞ安心して服用して下さい。
なおこの薬の内服により胃腸内の細菌叢が変化することにより、ときに下痢症状が発症することがありますが、そのような場合には服用する量を加減していただければすぐに元に戻ります。
Q:アトピー性皮膚炎では食事にはどのような注意が必要ですか?
アトピー性皮膚炎ではさまざまな刺激に敏感になり痒みが増強します。痒みが強くなると掻き壊しにより湿疹が増悪します。食事も痒みを増悪させる重要な要因です。とくに幼児では食事に対する反応が強く生じやすく、検査でも高頻度に陽性反応を認めるようになります。小学生頃には胃腸の状態が安定してくるので、食事に対する陽性反応の頻度は減少します。
基本的にアトピー性皮膚炎は食事が原因で発症する疾患ではなく、皮膚が弱いと同時に胃腸の粘膜も弱いために発症する病気です。そのため喘息や眼や鼻のアレルギーを発症しやすく、食事に対しても敏感になるのです。
十数年以前にはアトピー性皮膚炎の食物アレルギーの部分が強調され、厳密な食事療法が推奨されたこともありました。しかし、最近はそのような厳密な食事療法はあまり意味がないことが明らかになってきており、アレルギー性疾患の専門施設では厳密な食事療法はまったく行われていません。
乳幼児の場合には検査にて種々の食物抗原に対して陽性反応を示しますが、それは原因というよりも胃腸が敏感なためにその食物を食べた結果として反応が出ているだけであり、食物抗原に対する検査自体を行うこともあまり意味がないと考えられてきています。
しかし、とくに風邪などに伴って胃腸の状態が不安定になっているときには食事により痒みが増強することがあるのも事実です。一般に痒みが強いときには牛乳・卵・大豆などのほか、刺激物などの摂食は控えるようにしたほうが良いでしょう。
近年は種々の食品添加物が粘膜を刺激してアレルギーの発症を誘導することが知られています。合成保存料や着色料を使用した食品の摂取は避けるようにしたほうが良いでしょう。
Q:母親が卵を食べると、母乳を飲んだ乳児に湿疹ができるって本当?
卵や牛乳などのたんぱく質を含む食品を摂食した場合に、そのたんぱく質が完全に分解されないで消化管から吸収されて血液中に入るということについてはかなり一般に認められています。とくに風邪などにより胃腸粘膜が弱っている場合には粘膜からのたんぱく質の吸収が亢進しているために、食事性の蕁麻疹がたいへん発症しやすくなっています。
しかし、そのように血液中に入ったたんぱく質の量は極めて微量であります。母乳中に含まれるたんぱく質は乳腺細胞により新たに合成されたものであり、微量な食事性のたんぱく質が母乳に移行するということはけっしてありません。これはアトピー性皮膚炎の原因を食事性と考える学説を支持する医師が、母乳のみにて保育されている乳児に見られる重症の湿疹の原因を説明するために考えられたもので、まったく根拠のないものです。
たしかに乳幼児では検査で食事抗原により陽性反応を示す頻度が高いのですが、現在はアトピー性皮膚炎の原因を食事単独に求めることはまったく行われていません。ですからアレルギー専門医が厳密な食事制限を指導することもありません。
生後2~3ヶ月の乳児に認められる強い湿疹形成の主な理由は、乳児において急速に形成されつつある腸内細菌叢から産生される内毒素の影響と考えられています。母体内で無菌的に発育した胎児は、生後種々の細菌に暴露され、消化管内で急速に増殖を始めます。この消化管内の細菌が種々の毒素を産生するために乳児に湿疹が形成されるのです。そのような理由により、湿疹症状の強い場合には腸内細菌の増殖を抑制またはコントロールする治療を行うこともあります。
Q:蕁麻疹やアトピー性皮膚炎の症状が強い場合には食事はどのようにしたら良いでしょうか?
蕁麻疹やアトピー性皮膚炎においては食事は重要な増悪因子の一つです。最近の考えでは、あまり厳密な食事療法は必要ないと考えられていますが、症状の強い場合には多少は食事制限したほうが良いでしょう。とくに食後30分~2時間の間に掻痒が増強する場合には摂食した食事の内容を検討する必要があります。一般に牛乳、卵、大豆などは蕁麻疹を誘発しやすいと考えられていますが、その限りではありません。意外な思い掛けないものが原因であることもありますので、食後に痒みが出たときには、その前に食べた食物をメモしておくことも重要です。
統計的に蕁麻疹を起こす頻度の高い食物は鶏卵、乳製品、小麦、果物(キウイ、バナナ、モモなど)、そば、エビ、魚類(イカ、ブリ、タコ、サケなど)、ピーナッツ、魚卵(イクラなど)、肉類、大豆、木の実類です。
基本的には胃腸粘膜の乱れにより発症するものですので、胃腸に刺激のある香辛料の強い食物は控えたほうが良いでしょう。またアルコールは胃腸の粘膜を直接刺激するほかに、血行を良くして掻痒を増強するので控えたほうが良いでしょう。
ほうれんそう、なす、そば、たけのこ、松茸、里芋、魚介類には仮性アレルゲンと呼ばれる成分が含まれていることがあり、非特異的に掻痒を増強することがあります。魚介類・肉類による蕁麻疹の場合には食物そのものよりも中に存在していた寄生虫のために発症することもしばしばあります。
防腐剤、合成着色料などの食品添加物によっても掻痒や蕁麻疹が誘導されることがありますので注意してください。症状の強い場合にはお菓子などの加工食品の摂食はなるべく控えるようにして下さい。
ときに食品中のサリチル酸誘導体が慢性じんま疹の原因になることがあります。トマト、ブドウなどで掻痒が増強する場合には注意が必要です。魚やエビ・カニ、山芋などで蕁麻疹が発生する場合には、調理中に手指に刺激が加わって蕁麻疹様の痒い紅斑が出現することがあります。
Q:アトピー性皮膚炎では、入浴剤はどのようなものを使用したら良いのでしょうか?
アトピー性皮膚炎には乾燥の強いタイプと痒みの強いタイプの2種類があります。どちらのタイプに属するかによって、どのような入浴剤を使用するべきかが異なってきます。
通常市販されている入浴剤の多くは保温を高めるのに重点が置かれています。また角質をなめらかにする成分も含まれています。これらの成分は一般の方には暖まって快適なものなのですが、乾燥が強く刺激に敏感な皮膚には逆に湿疹を増悪させることがあります。また保温効果が高い入浴剤は暖めて痒みを増強させます。
痒みが強いが皮膚の乾燥粗雑がひどくない型のアトピー性皮膚炎の場合には、特別な入浴剤は必要ありません。あまり熱い風呂や炭酸ガスなどを含んで保温効果を高めた入浴剤は痒みを増強するので避けたほうが良いでしょう。
乾燥や湿疹性変化が強い型のアトピー性皮膚炎では皮膚がたいへん敏感となっていますので、通常の入浴剤のみならずさら湯でさえも湿疹を増悪させることがあります。このような場合には皮膚保護作用のある油性成分を含んだアトピー性皮膚炎専用の特別な入浴剤を使用することが推奨されます。このような入浴剤は油の粒子を豊富に含み、湿疹のある皮膚をやさしく包んで保護してくれるので、さら湯よりも湿疹に対しては刺激が少ないのです。しかし、このタイプの入浴剤の場合には油を多く含むため変性しやすく、入浴剤を含んだ風呂の焚きかえしを行うことは勧められませんのでご注意下さい。
当院ではアトピー性皮膚炎用の入浴剤の試供品をおいてありますので、ご希望の方はお申し出ください。
Q:アトピー性皮膚炎では石鹸はどのようなものを使用すれば良いのでしょう?
アトピー性皮膚炎は基本的に皮膚が敏感であることにより発症する疾患です。石鹸も皮膚を刺激することがありますので、注意して使用する必要があります。しかし、アトピー性皮膚炎では汗や垢の刺激により湿疹が増悪することも指摘されています。そのため、不潔にしておくこともアトピー性皮膚炎の増悪につながります。
湿疹の状態にもよるためいちがいには言いにくいのですが、基本的にはアトピー性皮膚炎では入浴や石鹸洗浄は毎日行ったほうが良いと考えられています。しかしその際に、ゴシゴシと強くこすったり垢すりのような刺激を加えることは禁物です。石鹸もなるべくおだやかなものを使用して、柔らかいタオルで軽く洗うか、素手に石鹸を取って洗うようにするのが良いでしょう。
石鹸は皮膚に優しい低刺激性または弱酸性の石鹸を使用するのが良く、アルカリ性が強く洗浄力の強い石鹸はなるべく避けたようが良いでしょう。
当院では石鹸の試供品なども揃えてありますので、ご希望でしたら受付にご相談下さい。
Q:アトピー性皮膚炎では保湿剤はどのようなものを使用したら良いのでしょうか?
アトピー性皮膚炎で痒みがあるが皮膚の乾燥はそれほど強くない型の場合には保湿剤はそれほど気にする必要はなく、痒みを抑制することに重点を置くことが必要です。アトピー性皮膚炎で乾燥粗雑が強い型の場合には、乾燥を抑制するために適当な保湿剤を使用することが勧められます。
一般に痒みや赤みが少なく、皮膚の細かい落屑を主体とした乾燥性皮膚の場合には通常の保湿クリームやつばき油などの油脂を入浴後に外用することで十分です。
しかし痒みが強く湿疹性変化を伴っている場合には保湿クリームや油脂では痒みを抑制する効果に乏しく、逆に湿疹を増悪させることがあります。そのような場合には湿疹を改善させるためにステロイド剤などを配合した保湿剤を使用することが適当です。
湿疹が高度になると保湿剤そのものの刺激性が無視できなくなります。そのような場合には保湿剤の使用は中止し、ワセリンなどの皮膚を保護する作用の強い外用剤を主体とした治療を行うことが必要です。湿疹が改善してきたら、徐々にワセリンから保湿剤の外用剤に弱めていくことが可能です。
保湿剤であるから安全で副作用が生じないと考えることは間違いで、使用方法を間違えるとかなり強い副作用を生じ、湿疹が増悪します。保湿剤だからといってまんぜんと使用するべきではなく、症状に応じて適宜使用する外用剤を選択していくことが必要です。
Q:軟膏の塗り方について教えて下さい。
軟膏の塗り方は病気の状態にもよるために、なかなかいちがいには言いにくいところがあります。基本的には皮膚を保護する作用のある油性の軟膏は少しべたつき感が残る程度にやや厚めに塗布するようにします。それに対してサラッとしたクリーム状の軟膏は白さやべたつき感がほとんどなくなる程度に薄く延ばして使用します。
また軟膏を使用する皮膚の状態によっても使用方法が異なります。カサカサしているような場合には少し厚めに塗布して、かさつきを抑制するようにします。軟膏を塗布して角質がたくさん浮いてきたような場合には、いったんその軟膏を拭き取ってからもう一度塗布することも行います。ジクジクして滲出液が多く認められる場合には軟膏はできるだけ厚めに塗布するか、ガーゼに伸展して貼付するようにします。かさぶたが付着している場合には、かさぶたをマッサージしながら軟膏を擦り込みます。
皮膚が敏感になっていて赤みや疼痛が強い場合には、軟膏はあまり強く擦り込んではいけません。やさしくなでるように塗布して下さい。皮膚が硬く盛り上がっていて赤みがほとんどない場合には、多少強く擦り込むようにすることが必要です。
いずれにしても、皮膚の状況によって軟膏の塗り方も適宜変更することが必要になりますので、詳しいことについては当院の医師または看護婦にご相談下さい。
Q:子供が粉薬を飲まないのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
当院で処方している小児用の内服薬は多少甘味を持たせているので粉のままで服用してもだいじょうぶですが、味覚に敏感なお子様の場合には嫌がることもあります。そのような場合には、りんごジュースやネクター、ポカリスエットなどに溶かして飲ませてみてください。砂糖を溶かして甘くした水に溶かしても良いでしょう。グレープフルーツジュースやオレンジジュースの場合には苦味がかえって強くなることがありますので溶かさないほうが良いでしょう。ミルクや牛乳に溶解した場合に薬剤の効果が低下する可能性がありますので、勧められません。
それでも嫌がる場合には、ヨーグルトやゼリーなどに混ぜてみることも有効です。アイスクリームなどに混ぜると、その冷たさにより味覚が弱くなるので薬臭さが消えることもあります。
みそ汁やスープに混ぜることも可能ですが、あまり熱い汁物ですと薬剤が変性して効果が低下することがあります。少し冷ましたものに溶解するようにしてください。いろいろと工夫してみて、よろしければうまくいく方法について教えてください。
Q:わきがの治療方法について教えて下さい。
わきがは腋窩のアポクリン汗腺に嫌気性細菌が増殖して、その細菌の分解産物により独特の臭気を呈するものです。
思春期にアポクリン腺が急に成長する時期に発症しやすいのですが、このような思春期のわきがはほとんどが一過性であるために、成長とともに徐々に改善していきます。この場合には細菌の増殖を抑制する外用剤を塗布するのみにて改善することがほとんどです。症状が強い場合には内服薬を併用することもありますが、それ以上の治療を行う必要はほとんどありません。
体質的にアポクリン腺の分泌が盛んな場合には、成人になってもわきがが持続することがあります。やはり外用剤や内服にて治療しますが、なかなか改善しないこともあります。そのような場合にはイオントフォレーゼや手術により治療を行います。イオントフォレーゼは腋窩に電極を当て、通電することによりアポクリン腺の活動性を抑制しようとする治療法です。治療時に通電による疼痛がありますが、副作用はほとんどありません。
これらの保存的な治療によっても改善が認められない場合には手術治療が行われます。手術は腋窩に局所麻酔を行い、切開した後に皮下脂肪組織に存在するアポクリン腺をそぎ取るようにして切除するものです。治療効果はかなり高いのですが、手術による瘢痕を形成することがあります。また切除が不十分な場合には完全にわきがが消退せず、再発を認めることもあります。実際には皮膚のアポクリン腺の分布はかなり人によってまちまちであるために、完全に取りきれないで再発することが3~4割はあると考えたほうが良いでしょう。
Q:ピアスの穴を開けたいのですが、方法や費用について教えてください。
ピアスの穴開けは当院では注射針を用いて行っています。これは専用のピアス穴開け器(ピアーサー)よりも正確な位置調整が可能であることによります。通常は耳朶のほぼ中央部に穴開けしますが、希望により耳朶の辺縁に偏った開け方や複数の穴開けも行います。
注射針にて穴開けした後にはプラスチックのピアスを挿入します。これは約1週間程度の間、挿入したままにしておきます。ピアス穴の内部でほぼ上皮化が完了した時点で抜去します。この方法によりピアスによる湿疹の発生が少なくなります。
ピアス穴開けは自費診療になります。当院では以下のような料金設定です。
- 基本手技料1,500円/片耳、(ピアーサー持ち込みの場合は1,000円/片耳)
希望により麻酔による鎮痛処理を行います。穴開け後の感染予防のために、希望により消毒剤、抗生物質を処方します。
- 消毒剤120円、抗生物質1,440円(5日分)を申し受けます。
なお未成年者の場合には、保護者の同意を必要とします。
Q:下肢静脈瘤の治療法はどのようにするのですか?
下肢静脈瘤は下肢の静脈の逆流を防ぐ弁が正常に働かなくなったために静脈が高度に腫大してしまった状態です。妊娠や立ち仕事などにより下肢静脈に過度の圧力が加わった場合に発症しやすいため、女性に多く認められます。治療法としては、従来は静脈を全部抜き取ってしまうやや大がかりな手術がよく行われていたのですが、最近はより安全で苦痛の少ない硬化療法が行われるようになりました。
これは拡張した血管内に糊のような役割をする薬剤を注入し、静脈をつぶしてしまおうというものです。手術とは異なり注射針を刺入するだけですので疼痛は軽微で、副作用はほとんどありません。入院も不要で、外来通院にて容易に行うことができます。しかし静脈の拡張が高度な場合にはなかなか静脈が閉塞せず、一度閉塞しても再発しやすい欠点があります。そのような場合には拡張した血管の上部を手術により縛ってしまうことも行われています。
方法は下腿の拡張した静脈に薬剤を注入し、包帯にて圧迫固定するだけのものです。約5~10分程度の処置で、そのまま帰宅することが可能です。ただし処置当日は入浴は行わないで、翌日再診する必要があります。さらに症状が強い場合には静脈の上部で結紮する手術を行います。この場合には局所麻酔を行って下腿の上部を一部切開し、静脈を縛った後に切開した部位の縫合を行います。
Q:手術の方法と費用について教えて下さい。
皮膚の病変は皮膚表面にあるために比較的容易に手術を行うことができます。当院でも各種の手術を施行していますが、ほとんどは外来にて手術を行い、通院にて手術後の管理治療を行っています。しかし、やや大きな手術の場合には入院にて手術を行う必要があります。その場合には須賀川病院に入院していただき、院長が須賀川病院に往診して手術及び術後管理を行うことができます。
大部分の皮膚科手術は局所麻酔にて行われます。これは病変部の周囲に麻酔薬を注射して行うもので、麻酔時に注射による疼痛がありますが、速やかに麻酔効果が現れ、意識も清明ですので手術中に医師との会話も可能で、手術後すぐに帰宅することができ、麻酔が切れた後の疼痛も軽度です。
手術の方法については病変の状態によるため一概には言えませんが、皮膚ガンの手術や皮膚移植手術などを含めて各種手術を施行することが可能です。手術にかかる費用は、手術後の傷の大きさにより算定します。概算にて以下の通りです。悪性腫瘍の手術や特殊な手術の場合にはこの限りではありません。
| 自己負担割合 | 2センチ未満 | 2~4センチ | 4センチ以上 |
| 1割負担 | 約2,500円 | 約4,500円 | 約5,500円 |
| 3割負担 | 約6500円 | 約12,000円 | 約15,000円 |
これにさらに、抗生物質などの内服薬や外用剤の薬剤費が加算されます。手術に際しては、細心の注意を払ってできるだけていねいに行っておりますが、ときに不測の事態が生じたり、手術後に瘢痕を形成してしまうことがあります。あらかじめご了承下さい。